
焼酎道場「壱號蔵」を語る【後編】
壱號蔵でつくったこだわりの
本格麦焼酎「重露涓滴(ちょうろけんてき)」
対談:三和酒類相談役 和田久継×技師 丸尾剛
社内研修プログラムの焼酎づくり体験で使う「壱號蔵(いちごうぐら)」に、焼酎製造のベテラン社員が集結。かつて製造部長も歴任した相談役の和田久継(わだ・ひさつぐ)を中心に、理想とする本格麦焼酎「重露涓滴(ちょうろけんてき)」をつくり上げました。これまでの経験を注ぎ込んだ逸品。「今回の重露涓滴をつくり上げる経験はみんなの財産になった」と技師の丸尾剛(まるお・つよし)は語ります。「重露涓滴」の開発経緯、完成までのプロセスを追います。 前編「実際に社員が手を動かして焼酎づくりを学べる施設をつくりたかった」 文:鈴木昭
革新的酒づくりにチャレンジする場「酒の杜21製造場」
――「壱號蔵」の話(焼酎道場「壱號蔵」を語る【前編】)にも出てきた「酒の杜21製造場」というのはどんな施設なのでしょうか。「壱號蔵」のすぐ隣にあるんですね。
和田 酒の杜21製造場は1999(平成11)年に、新しい焼酎製造の技術を取り入れるために設立しました。当初は「酒の杜21世紀工房」と呼んでいました。
丸尾 将来に向けて、現行の主力商品とは一線を画す酒質を生み出すことがミッションです。本社のほかの製造場で使われている仕込み規模と比べるとおおよそ18分の1程度の規模で、革新的な酒づくりにどんどんチャレンジしていくという狙いでつくられました。
本社にあるメインの製造場の規模は28t(28,000kg)あり、酒の杜21製造場の規模は1.5t(1,500kg)です。このサイズでトライしていくわけです。ちなみに、「壱號蔵」の仕込み規模は150kg。酒の杜21製造場の仕込み規模と比べるとさらに10分の1のミニサイズですね。三和研究所では何mgといった小さな装置も使われているんですよ。
――これまでに、酒の杜21製造場から生み出された商品にはどんなものがありますか。
丸尾 セブン&アイ・ホールディングスさんと共同開発した「いいちこ大地のつむぎ」やファミリーマートさんと共同開発した「いいちこ円熟」、そして業務用ルートで卸している「杜翁(もりのおきな)」などがあります。
和田 大分麦焼酎®「西の星」が最初につくられたのも酒の杜21製造場(当時は酒の杜21世紀工房)でした。地元・大分県宇佐市産の二条大麦「ニシノホシ」を使って試験的に仕込むのに規模的にちょうどいいということで、最初にここで製造して、その後、製造量の拡大に対応して本社のメインの製造場にスケールアップしたという経緯でした。
杜甫の詩にインスパイアーされた
本格麦焼酎「重露涓滴」
――今年7月に三和酒類から「重露涓滴」という数量限定の本格麦焼酎(アルコール度数44度)が発売されました。この製造には「壱號蔵」の設備を使われたのですね。
和田 自分の理想とする酒のイメージを少量生産で実際に形にしてみたいと考えました。酒の杜21製造場のサイズでは大き過ぎて、「壱號蔵」のサイズがちょうどよかった。丸尾さんのほか、焼酎製造に携わる方々に集まってもらって、「私も(会長を)退任するけん、今までの集大成としてつくりたいんやけど」という話をしました。
丸尾 「重露涓滴」プロジェクトのキックオフは2023年9月13日のことです。いまから2年前のことでしたね。その時に和田相談役から見せてもらった酒のイメージの紙は、事務所の壁にずっと貼られていたものなので、気にかけていました。
和田 こういうお酒をつくってみたいなあ、というイメージを、A4サイズ1枚にまとめましてね。これ。これです。
 和田相談役が中国の杜甫の詩「倦夜」に触発されて作成した酒のイメージメモ
和田相談役が中国の杜甫の詩「倦夜」に触発されて作成した酒のイメージメモ
今までに無い焼酎の味 軽やかな香りで口に含むと とろっとした旨味が拡がってくる。
のどを通過するときにはその快感に感動する。そんな焼酎を飲んでみたい。
――お酒のイメージというのは、最初はこういった言葉で表現するものなんですね。
和田 はい。言葉なんです。こういうイメージの焼酎をつくりたいなあ、というところから始まって。そのためにはどういうつくり方をしたらいいかを考えます。最初は言葉なんです。
杜甫(とほ)*1の「倦夜(けんや)」という詩の中の、「重露成涓滴(ちょうろ けんてきをなし)」というね。重露というのは、竹の葉先におりる露のことで、涓滴というのは葉先にたまりポタリと落ちる水滴のことです。どこでこの杜甫の詩に出合ったのか覚えていないんですけれど。たまたま見つけたこの詩がいいなあと。その情景が浮かんできましてね。
この詩を焼酎で表現したらどういう酒になるのかな、ということを文字にしたのが、この酒のイメージです。で、集まってもらった焼酎製造に携わるメンバーに、「こげな焼酎できんじゃろかな?」と話を持ちかけたんです。*1 杜甫:712〜770年、中国、唐中期の詩人。「詩聖」と称され、「詩仙」と呼ばれた李白(りはく)とともに唐代の代表的詩人。
 和田久継(わだ・ひさつぐ)相談役(写真:三井公一)
和田久継(わだ・ひさつぐ)相談役(写真:三井公一)
 丸尾剛(まるお・つよし)技師(写真:三井公一)
丸尾剛(まるお・つよし)技師(写真:三井公一)丸尾 頭の中ですぐにイメージできました。それから逆算していけば、こういったつくりになるというのは、我々つくり手の中ではそれぞれシミュレーションできます。蒸留はこうして、酵母はこれを使って、仕込みはこんな感じで、という調子で。お互いにその工程イメージを持ち寄って、10本、サンプルの原酒を用意して、一つ一つ試飲して確認しながら、製造工程の手順などを決めていきました。
中でも麹にはよりこだわろうと強く思いました。それにはわけがあります。私がまだ20代の頃の話です。当時、和田相談役は製造部長だったと思います。本格焼酎の業界全体が大いに盛り上がっていまして、三和酒類の製造現場でも、焼酎づくりの技術開発が進化している過程でした。その時期に和田相談役がこうおっしゃった。

「もろみは麹の酸で守れ、麦は麹の酵素で溶かせ」
要するに、和田相談役は、麹そのものを究めていって、麹の力そのものでいい焼酎をつくるんだ、ということを当時おっしゃったんです。
その言葉がバイブルとなり、その想いでこれまでずっと酒をつくってきました。だから、和田相談役から、「重露涓滴」のお話をいただいたときに、麹については、今までの麹づくりの技能の集大成ということで取り組もうと決断しました。
――麹づくりの技能の集大成とは具体的にどんなことでしょうか。
丸尾 これまでの経験の中で得た、自分たちが「重露涓滴」に一番適すると考える技能、方法で麹をつくろうと。機械まかせではなくて、絶えず麹の状態を見ながらね。麹室の温度は、遠隔でモニタリングしながら、プロジェクトメンバーの3人で常時監視しながら、自宅でもずっと温度を確認していました。
和田 それは、みんなに相当迷惑をかけたなあ。
丸尾 いやいや。それが後々の酒質に関していい方向に向かっていったのですから。この取り組みを機にメンバーの焼酎づくりに対する考え方も変わりました。この経験はみんなの財産になりました。

――麹づくりから出来上がりまでどのくらいかかったのですか。
丸尾 2023年11月に第一弾の仕込みをやってみました。それを受けて、本番の仕込みが2024年1月18日。本番前に1回仕込みをやっておいて良かったなと思いましたよ。いきなり本番というのは正直なところ難しかった。仕込みには和田相談役にも作業に加わっていただいてね。
和田 杜甫の格好して行こうかなと思ったんですけれどね(笑)。神事もあったのでやめました。みんなで楽しくやろうよと。中身からパッケージデザインまで妥協せず、かなりこだわりましたね。皆で議論を重ねました。ちょっとでも妥協すると全て駄目になると。だからこだわっていきましょうよとね。
――最初に出来上がった原酒を口に含んだ時の印象はどんなものでしたか。
和田 98%、99%まではいいんだけどなあ、という感じでした。1%、2%が足りんなあと。最後ののどをすっと通る時の快感というあたりが足りんなあと。

――その最後の足りない部分はどのように解決されたのですか。
和田 それはね、企業秘密です(笑)。
丸尾 はい、マル秘です。それが本当に効いたし、大きなポイントでしたね。
和田 いままでの三和酒類の商品づくりを補うために参考になる部分ですね。

 数量限定の本格麦焼酎「重露涓滴(ちょうろけんてき)」。アルコール分:44%、希望小売価格:16,500円(税込)、内容量:300ml。「いいちこ日田蒸留所」(日田市西有田810-1)と「辛島 虚空乃蔵」(宇佐市辛島4-3)、三和酒類オンラインショップでご購入いただけます
数量限定の本格麦焼酎「重露涓滴(ちょうろけんてき)」。アルコール分:44%、希望小売価格:16,500円(税込)、内容量:300ml。「いいちこ日田蒸留所」(日田市西有田810-1)と「辛島 虚空乃蔵」(宇佐市辛島4-3)、三和酒類オンラインショップでご購入いただけます
――企業秘密の手立てを施して、いよいよ「重露涓滴」の原酒が出来上がりました。その時はどんな印象でしたか。
和田 「これやな」と。
丸尾 2024年の11月です。その前に酒質の確認なども終えて、2024年1月29日にろ過があがり、貯蔵。そこから3月、4月、5月とチェックをして。最後に商品のアルコール度数を決めようと。40度にしたり、35度にしたり、30度がいいのかとか試してみて。
和田 結局、44度と度数が高い方が、最初のイメージに合ったようです。
丸尾 30度にしたときと44度にしたときと、飲み比べてみて、そのとろっと感ですね。それが全然違いましたね。
和田 そうそう。とろっと感。だから、「重露涓滴」はストレートを試してもらいたい。

PROFILE
和田久継(わだ・ひさつぐ)
三和酒類株式会社 相談役
1953(昭和28)年、大分県宇佐市生まれ。1976(昭和51)年3月、高知大学農学部卒業後、三和酒類株式会社入社。主に製造畑を歩み、役員として製造担当などを歴任。2009(平成21)年、代表取締役社長、2017(平成29)年、代表取締役会長に就任。専門分野は醸造技術(本格焼酎、日本酒、果実酒等)、製造用プラント設計。2023(令和5)年、相談役に就任。一般社団法人宇佐市観光協会会長(現職)、公益社団法人ツーリズムおおいた会長(現職)など地元活性化にも取り組んでいる。山歩きや野鳥観察などを好むアウトドア派。

PROFILE
丸尾剛(まるお・つよし)
三和酒類株式会社 SCM本部 技師
1965(昭和40)年、大分県宇佐市生まれ。1984(昭和59)年の入社以来、一貫して焼酎づくりに取り組む蔵人。2012(平成24)年8月から5年3カ月の間、いいちこ日田蒸留所の所長を務め、「いいちこ日田全麹」のリニューアルに携わる。現在も現場に立ちつつ後進の指導を行う。趣味はゴルフ。家で塩麹、醤油麹を自作するほどの麹愛の持ち主。また「“酒場メシ”ハンター」の異名を持ち、「いいちこ」をもっと楽しんでいただくための情報サイト「iichikoスタイル」では「いいちこ丸尾の“酒場メシ”いただきます!」の連載を担当。
製作者インタビュー(ボトル製造)慣れるまでは苦労します。慣れてしまえば、あとはもう感覚です
有限会社マイハラ製作所
舞原利夫

――「重露涓滴」のボトルを製作されてみて、どんな印象でしたか。
ふだん製作しているのはフラスコなど理化学用機器のガラス器具です。この「重露涓滴」のボトルづくりもその延長線上の感じでした。でも、用途が全く違う分野で、自分のつくった製品がお客様に使われるということにうれしさを感じますね。
――日々のガラス製品づくりの面白さはどんなことですか。
いろいろな製品のご依頼を受けますので、日々修練という気持ちで取り組んでいます。その都度、課題をクリアできれば、本当にうれしいものですし面白さもそこにありますね。実は稀ですが失敗もあるんですよ。ですから、形になった時の喜び、達成感というものは毎回感じます。
 バーナーで熱してフラスコ(本体)底面を平面にする
バーナーで熱してフラスコ(本体)底面を平面にする フラスコ(本体)の首径をボトル首管の径に修整
フラスコ(本体)の首径をボトル首管の径に修整 熱で柔らかくして接合
熱で柔らかくして接合 本体と首の部分が接合された
本体と首の部分が接合された
――さっき、ボトルの首管の部分とフラスコ(本体)の部分の接合の工程で、木槌のような道具を使って中心を合わせていましたが、うまく合わせるコツがあるのですか。
そうですね、ガラス旋盤*2に固定して芯出し*3する作業は、感覚ですね。これは慣れていくしかない。やったことのない人は感覚をつかむまでは苦労します。私も最初はそうでしたけれど、慣れてしまえば、もう、だいたいの感覚です。感覚がものを言います。*2 ガラス旋盤:ガラス管やガラス棒を回転させて、バーナーの火炎で加熱しながら加工する機械。精密なガラス器具の製作に使われる。
*3 芯出し:固定したガラスの中心部分と機械の回転軸(主軸)の中心部分とを合わせる作業。

PROFILE
舞原利夫(まいはら・としお)
有限会社マイハラ製作所 社長
1972年、埼玉県久喜市生まれ。高校卒業後、都内の理化学機器メーカーに勤務しガラス加工技術を習得。2004年、父の舞原治さんが越谷市に設立したマイハラ製作所に入社。2010年、同社社長に就任。
製作者インタビュー(ボトル製造)の写真:三井公一















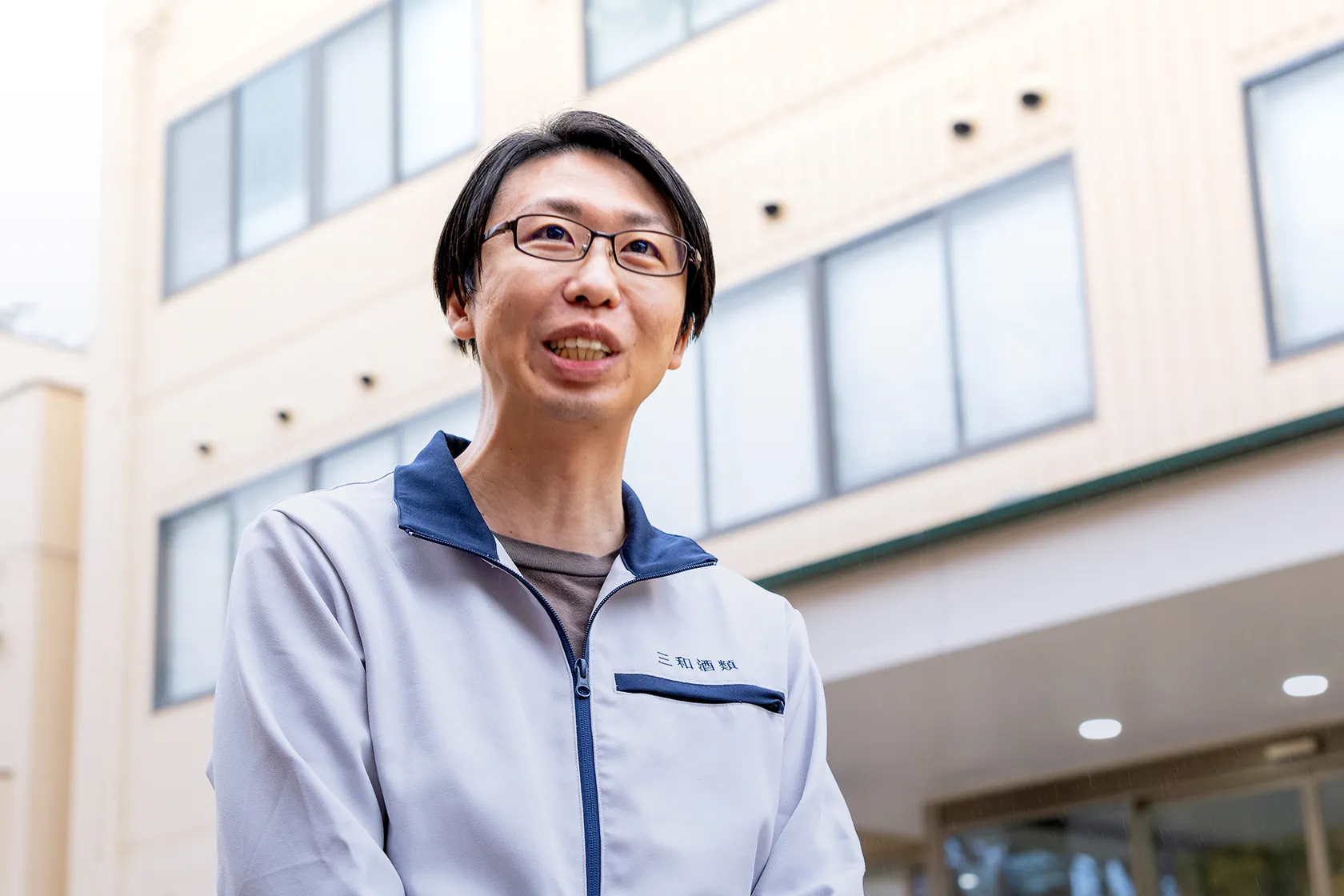

















![大分の歩きたくなる道[from OITA 大分を巡る]](/kojinote/common/images/recommend_oita.jpg)

![三和酒類[by SANWA SHURUI 三和酒類の酒造り]](/kojinote/common/images/recommend_sanwa.jpg)

![東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻教授 太田博樹[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji.jpg)

![Dr.下田の新本格焼酎論 第4回[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji_s.jpg)
![お笑い芸人 えとう窓口(Wエンジン)[with PEOPLE 縁ある人たち]](/kojinote/common/images/recommend_people.jpg)




